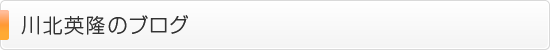円高メリットを活用できたのか
リーマンショック以前、円は売られていた。米ドルに対してはともかく、他の通貨に対しては20年以上前に遡らないといけないくらいに安かった。その時は心配で、ろくすっぽ夜も寝られなかった。
というのは冗談だが、でも円が安くなると、老後の生活には大きな影響が生じかねない。直接的には、海外旅行が高くなる。物価も高くなるだろう。そんなこんなで、年金で生活しようという計画に齟齬が生じてしまう。だから、老人にとって円高は歓迎すべき状況である。円高に伴う株安、株安による年金財政の破綻、さらには企業倒産が誘発されれば別だが。
それはともかく、本日(9/17)の日経夕刊の十字路は適切なコラムだった。日本経済が円高のメリットを十分に活かしてこなかったのは事実である。私自身、『総合分析 株式の長期投資』で日本企業が円高で貧乏になったと分析しているが、その分析が適切なのかどうか常に反芻していた。「そんな反芻なんて不要では」という声が本日の十字路から聞こえてきた。
要するに、日本の製造業と従業員は円高に対して身を削り対応してきたのである。身を削る必然性はないのだが、「円高→大変→何とかしなくちゃ」(最近の学生の期末試験に対する答案のような書き方だが)ということで、自らの製品や労働力をダンピングしてしまった。円高は、原材料を安く買いたたき、誰でも製造できる製品を安く輸入し、自らは独自の技術に磨きをかけるチャンスだった。なのに、誰でも製造できる製品も自分で引き続き製造しようとあくなき努力をしてしまい、無用な安売り競争に引き込まれたのである。それまで製造してきた製品以外をイメージできなかった、つまり経営者の発想の貧困が原因かもしれないが。
日本経済にとって、人口の高齢化、乏しい資源、その中での円高は、日本産業が高付加価値化すること整合的である。高付加価値化を促していた。しかし現実は、逆に低付加価値化してしまったとしか言いようがない。教育もまた、ゆとり教育、ばらまき教育で、低付加価値化を後押しした。そもそものところ、1970年代の後半からの、円高は好ましくないという極めて短期的な評価に基づく政策対応が尾を引いているのかもしれない。
2010/09/17