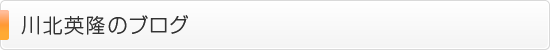株式の高速取引は何のために
中央経済社「企業会計」10月号の巻頭に加護野忠男「会社統治制度改革はなぜ失敗したのか」があった。同意できない部分はあるものの、証券市場に関するコメントは「その通り」である。
前半は資本市場制度に関する全体像である。英米型と日独型の比較であり、経済的、社会的パフォーマンスからは日独型資本主義が優れていると紹介されている。この紹介が、コラム全体の流れにおいて何の役に立っているのか、今一つ不明である。また、紹介された見解の結論は、日独型の方が優れているとのことだが、敗戦国である日独が戦勝国である英米の成功を真似たことの(割引の必要な)事実がどの程度考慮されているのかも不明である。英米という手本のあった日独が圧倒的に有利だったのだから。
また、役人や役員が秀才であれば、英米という手本のある場合に圧倒的効果を発揮できる。しかし、手本がなくなれば、東大卒に代表される秀才だけでは役立たない。そこそこの知識に、圧倒的な行動力が要求されるから、むしろ秀才では負けてしまうだろう。
これらの反論はともかく、後半に展開されている証券取引所の高速取引への批判は当たっている。加護野さんの主張を意訳すると、「瞬時の取引速度を争う取引所のインフラ整備が何の役に立つのか、大いに売買させて手数料を儲けようという戦後何十年も続いた証券会社根性の延長線上の改革でしかない」との見解である。「証券取引所は・・・短期投資家を重視する。バフェット氏のような長期投資家ではない」とも記されている。
かつて、株式アナリストをしていた時代、「もっと活発に売買しないと」と、知り合いの証券会社の兄ちゃん(当時はオッちゃんだったか)に諭されたことがあった。その瞬間、「余計なお世話」と思った。証券会社出身の人間は、短期売買とは言わないまでも反射神経を効かせて売買することが本筋と評価している。その評価が、骨の髄まで染みこんでいるのだろう。
加護野さんは「市場の合理性は、多数の異なった意見を集約することによって生み出される」とも書いている。反射神経に基づく売買を否定しないまでも、それが突出したのでは市場の発展はないとの見解であろう。当然であり、大いに同意できる。
証券会社はこれまで投資家の売買だけを促してきた。これでは市場にぺんぺん草が生えるだけ、証券会社の長期的な利益にならない。ぺんぺん草が生え、市場が細れば、証券会社は死に絶える。現在がまさにそうではないのか。証券会社も、証券会社の親分である取引所も、大いに反省すべきである。
2012/09/06