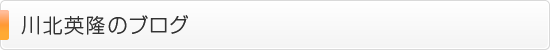「のれん」は償却か減損か
のれん(英語でgoodwill)、営業権とでも言い換えるのか、その会計上の評価が問題化している。国際会計基準の見直しである。まだまだ紆余曲折があるだろうが、議論の俎上に載ったのは大きい。
のれんについて簡単に説明しておく。会計上100億円の価値(純資産)があると処理されてきた企業を150億円で買えば、のれんとして50億円が生じる。のれんは買収した側の企業の資産として計上される。
もう少し正確に書くと、純資産を計算するためのベースとなった資産と負債の会計上の金額が、時価と等しいとの前提が必要である。現実には、少なくとも資産の再評価がなされるだろう。
また、100億円の企業を80億円が買えば、負ののれん20億円が生じ、利益として計上される。
会計上の問題となっているのは、(正の)のれんの場合である。のれんについて、日本の会計基準では20年以内の期間を定め、規則的に償却することとされてきた。一方、国際会計基準は償却を要請せず、のれんの価値が大きく毀損していないかどうかを判定し、大きく毀損しているのなら、減損処理を(つまり会計上の損失の認識を)すべきだと規定している。国際会計基準に限らず日本の会計基準でも減損処理の規定がある。とはいえ、日本基準の場合は毎年償却を実施しているので、減損の必要性の判断と、減損処理した場合の損失額とが国際会計基準とは異なってくる。
のれんに関する国際会計基準の大きな前提は、のれんの推計が容易だというものだろう。もう少し言えば、買収した事業であれば、その資産と負債の時価評価や、その事業資産が将来生み出すキャッシュフローの推計が容易だと想定している。本当なのか。
企業買収という非常に重要な意思決定においてよくある事実は、買収側の企業の判断が大きく間違ってしまうことである。「外部のコンサルを入れるのに」である。それほど、事業価値の評価は難しい。
僕自身がいくつかの企業価値評価を行った経験からは、極論ではあるが、結論(この金額であってほしいという結論)さえあれば、どのような評価でも可能だろう。実務的に多用されるDCF法(discounted cash flow 法)では多数の変数を設定しなければならない。このことが「幸い」する。数字の組み合わせが多いから、結論に合わせやすい。
減損処理が必要とされるのは、買収した事業部門が明らかに不振で、多くの場合は赤字に陥ったときだろう。それ以外の場合、たとえば黒字が多少減ったとか、計画していた黒字に届かない程度なら、「まだ将来性がある」という理由で、減損処理が先送りされるだろう。逆に、「今年は他の事業分野での利益が予想外に大きい」というので、将来への期待が残っている事業分野であるのに、それに対して減損処理が前倒しされることもありえる。
つまり、減損処理するかしないか、経営者の恣意性が強く出る。
国際会計基準は理想主義、原理主義の色彩が濃い。のれんを事例とすれば、事業価値の推計が正確に行えるし、会計関係者にその能力があるとの前提である。
中央大学国際会計研究科の紀要「CGSAフォーラム第16号」に「ファイナンスと会計上の見積もり」を寄稿した。国際会計基準が「なんでも時価で評価できるとの非現実的な全体に立つ」と議論を展開し(のれんを減損すべきかどうかも時価評価の1つなのだが)、「企業側が資産や負債の価値を見積もることはどの程度許容されるのか。相当限定的であるべきだと考えていい」と結論した。
のれんの議論に戻ると、時価評価が難しく、恣意性に陥りやすいとすれば、国際会計基準よりも日本基準の方が優れている。少なくとも、買収した事業分野の独自の価値(たとえばノウハウ)が10年も20年も存続することは夢物語である。とすれば、毎年のれんを償却することで、ほぼ近似的なのれんの評価が可能となる。
実務経験者や識者と議論したところ、上記で書いたことと同じような感覚だったことを最後に報告しておく。
もう1点、株式に投資する場合、国際会計基準を採用し、のれんが多額になっている企業には細心の注意を払う必要がある。いつ何時、多額の減損処理が発生するかもわからない。とくに業績が下降に向かったのなら、黄信号だろう。
2018/10/27