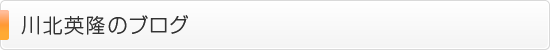超金融緩和の意味はどこに
日本が金融緩和状態に入って久しい。2007年に多少緩和から引き締めモードに入ったのだが、アメリカにサブプライムローン問題が生じて世界的な緩和モードにやむをえずして引きずり込まれた後、13年以降は先進国としてこれ以上は考えられない緩和に突入した。
まさに超金融緩和であり、さらに言えば空前絶後である。では、それによって何か良い事が生じたのだろうか。
カンフル剤的な効果があり、12年終盤以降、株価を中心に多少の明るさが生じた。もっとも、その明るさは中国やアメリカの好景気に支えられた面も大きく、日本が自分自身の手で明るくしたと大見得を切れないところが残念である。
この点、世界的な日本の地位の低下(たとえば一人当たり国民所得で韓国や台湾に追いつかれ抜かれようとしている状態)、その後の日本の株価に力強さがないこと、日銀が目指すとする消費者物価2%上昇(それも自律的な上昇)とそれに並行した意味のある賃金上昇が程遠いことなどから明らかである。
日経は1/5の紙面で前日銀総裁の白川氏インタビューを掲載している。そこで白川氏は「緩和効果の基本メカニズムは需要に先食いにある」「(日本経済の)低成長の原因は物価や金融政策ではなく・・潜在成長率の低下にある」としている。
この潜在成長率について、標準的な経済理論では、人口、資本(設備など)、技術(生産性の向上)によって決まるとする。
たとえば、日本の人口減少によって需要が減るため、潜在成長率が低下するとされる。しかし目を海の外に転じると、開拓できる需要は山のようにある。それを手にすればいいのではないか。
とはいえ、人口減少によって労働力が減るから、やはり潜在成長率の低下は免れないのではないか。この点は、経済全体としての労働力の配置転換(衰退産業から成長産業へ)と生産性の向上(1人の労働者が生む出す付加価値≒売上高のアップ)によってカバーできる。
そこで、日本の超金融緩和を個人の観点から少し考えてみたい。株価は上がったが、個人金融資産の大部分は預金や保険であり、個人には株価上昇の恩恵が届きにくい。預金しても金利がつかないから、超金融緩和は個人にとってかえってマイナスの側面が多い。企業業績はあまり冴えず、賃金が上がらない。このため個人は消費に走らない。ぼっちキャンプが流行るのには、金がかからないという要素が多分にある。超金融緩和によって需要がかえって減少しているのではないだろうか。
企業に目を転じると、日本には成長する企業が数少ない。成長する分野はアップルやグーグルに持ち去られ、アマゾンの後を付いていくだけである。日本企業は横の日本企業を見つつ、「アリバイ工作的」な投資しかやらない。電気自動車にしても、風力発電にしても、尻に火がつくまで何もしてこなかったに等しい。太陽光発電の主要部材(パネル)では中国に負けてしまった。超金融緩和は、労働力の配置転換や生産性の向上への絶好のチャンスを与えてくれるのだが、日本企業はそれを活かすことができなかったようだ。
政府もまた、超金融緩和に歩調を合わせた産業政策を打ち出せなかった。既存企業に「寄り添う」政策に終始しているため、競争させて企業を淘汰し、新しい産業を生み出す政策を打ち出していない。このためネット関連、IT関連で日本の負けが続いている。原子力発電に拘泥するあまり、世界的な電力革命に足を大きくすくわれた。医薬品について、薬価の引き下げという目先の政策に目を奪われていたため、ワクチンを含めた新薬の開発(そのための医薬品業界の長期的な育成)でも負け続きである。
まとめておく。超金融緩和は企業に安い資金を供給する。その安い資金を活かせる企業に新しい発展をもたらす。古い業務を切り捨てる企業に対しても、その切り捨て費用を、安い金利という形で支援してくれる。
では何が古く、何が新しいのか。その示唆を与えるのが政府の役割である。残念ながら最近の政府にはというか政治家には、その役割意識に乏しい。古い企業を潰すまいと「寄り添う」意識しかない。獅子の子を千尋の谷に突き落とす故事というか譬話を知らないのだろうかとさえ思える。
結局のところ、千尋の谷に突き落とされたのは個人である。預金金利ゼロという負担だけを延々背負っている。新しい技術環境に対する訓練も受けさせてもらえないから、チャットしかできないIT弱者が多数を占める。残念である。
2022/01/06