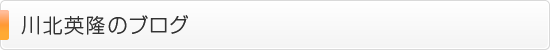今も続く殖産興業主義
先日、知人と意見交換をしたところ、「殖産興業」という用語が登場した。明治維新もそうだったし、敗戦後の復興もそうだった。産業を興すことで日本が富む、それが日本を強くし、国民が幸せになる。そんな政策であり、それが現在も続いている。
明治維新後、繊維で稼ぎつつ、西洋に追いつくために製鉄や造船などの重工業の育成が図られた。戦後の復興は重化学工業に中心が移り、電気機器やコンピュータがこれに続いた。今は半導体だろう。
戦時体制にあっては、民間企業が半ば国有化された。同時に金融業界も、政府が命令を出しやすいように合併が進められた。金融の統制であり、1940年体制とも称される。
戦後の殖産興業政策を推進したのが通商産業省(通産省、今の経済産業省)である。運輸省(今の国土交通省)などの所管産業もあったが、大部分は通産省の所管だった。
では殖産興業の特色は何にあったのか。産業育成のためには当面、国民に不便、不利益を与えても仕方ないとの考えである。その典型が「円高は敵」である。円高になれば企業が疲弊するからに他ならない。企業が疲弊すれば、勤労者が困るだろうとの理屈である。
この論理からは、円安で輸入物価が高くなるとの発想が消えている。円高になれば企業が生産性を上げるための努力を積み重ねざるをえず、その結果として日本企業の世界的な競争力がさらに高まるとの論理は念頭になかった。現時点において問題になっているような、円安は輸入物価高や「安い日本」を招く一方、生産性を上げられず、競争力に乏しい企業までもが生き残るという、いわゆるゾンビ企業の跋扈を想定できなかったわけだ。
殖産興業においては、日銀が決める政策金利も低いに越したことはない。預金金利が低くなったとしても、企業が設備投資のために調達できる金利を安くできるから、それが日本の成長をもたらすと考えた。ここでは、金利が極端に安くなってしまい、企業が無駄な投資をすることをイメージできなかった。この結果、1980年代後半のようなバブルを招いてしまった。
殖産興業は発展途上国の経済政策である。金融統制や低金利政策も同じである。1980年代に欧米に追いついた日本は、本来、その時点で新しい産業政策、金融制度を考え、形にする必要があった。それができないまま(模索はあったのだが、パッチワーク的なものしかできないまま)、今日を迎えている。
株式市場も例外ではない。100株単位でしか売買できない(単元株という屋上屋的な制度を残す)日本の株式市場とは何なのか。猫も杓子も株主になれれば、上場企業が事務的に困るからだという。「金融リテラシーだ、証券で財産形成だ」と言いながらも、政府と関係機関はいまだに一般の国民を向いていない。
「事務的に困るのなら上場しなければいい」との企業への反論は、殖産興業の論理では出てこない。「とりあえず単元株制度を止めよう、その上で数千円のみの投資で多数の株主が登場するのは困るという企業が出てくるのなら、その企業は自主的に今の10株もしくは100株を1株にまとめればいい」と、政府が提案すればいい。国民目線に合わせて政府が株式市場を設計する。そのうえで、企業の多様な判断を認めればいいだけのこと。
アメリカでは当然、1株から投資できる。多くの企業は1株100ドル台を意識している。とはいえ、ウォーレン・バフェット氏で有名なバークシャー・ハサウェイの株式(クラスA)は1株66万ドル以上している。その一方でバークシャー・ハサウェイは、クラスA株の1/1500の権利しかない(正確には、さらに権利がプラスアルファで制約されている)別クラス(クラスB)の株式も売買できるようにしている。一般の投資家はこのクラスB株に投資することになる。
現在、郵便や旧来的な書類を使わずとも、いろんな権利を行使できる。株券も無くなっている。知恵を絞れば(絞らなくてもアメリカの方法を参考にすれば)、事務も簡便になるはず。ということで、殖産興業というか企業を向いた行政ではなく、国民を向いた行政に期待したいものだ。
2024/08/18