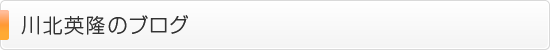配当と株主優待の変-1
「株式に投資するのなら配当や」とか「株主優待や」と騒がしい。本当なのか。否定はしないものの、やはり怪しい。株式投資の本筋ではないだろう。
そもそも論からすれば、株式に期待するのは企業の成長である。配当は成長の果実というか結果であり、企業が成長途上にある場合は「おまけ」でしかない。ましてや株主優待は「こませ」にすぎない。
これまでのところ、日本企業は配当に対する誤解の連続だった。それが今も続いている。
日本の高度成長の時代、日本企業は何の疑問を抱かずに誤解していた。「あげた利益は企業のものだから、その利益から支払う配当は株主に対する施しであり、企業からの厚意のようなものだ」と。もう少し言えば、「無配すなわち配当しないのは、さすがにダメ企業の烙印を押されるから、世間並みに1株5円の配当をしておこう」と企業は考えた。
実は当時、株式には(2001年に廃止になった)額面というものがあり、それが通常は50円だった。だから5円の配当とは、額面に対して1割(10%)に相当する。預金金利が3%とか4%の時代だったから、10%も配当をすれば「立派な企業で、お大尽と思われるかもね」と、企業は思ったのである。まあ当時は高度成長の時代だったから、配当した残り、いわゆる内部留保は企業が成長するための投資へと自然に回った。
高度成長が終わっても企業の意識はあまり変わらなかった。「稼いだ利益は企業のもの、ある程度の配当をしておけば株主は満足する」と。しかも1980年代に入り、株価は額面を大きく上回るようになったから、株価に対する配当の率は1%を割るようになった。
当時のこの現実を見て企業は、「株式のコストは非常に安い、株式で資金調達し、儲けた利益と合わせて不動産や株式をたんまり買い、しばらくして売却すれば大儲けできる、雪だるま式に稼ぎが増える」と踏んだ。いわゆる「財テク」である。その結末が1980年代後半のバブル形成と、90年年初から2000年代初頭まで続いたバブル崩壊である。
バブル崩壊に直面しても企業は反省しなかった。稼いだ利益を内部留保として抱え込み、いざという場合に備えた。本当のところは、企業が稼いだ利益とは株主のものであり、それを配当せずに内部留保とするなら、株主の期待に応えるために高いコストがかかる。この内部留保という高いコストの資金を用いるからには、企業が経営努力して成長すること、具体的には新規投資によって高い利益率を達成しなければならないのだが、その初歩の経営学的常識がなかった。
その結果、内部留保を現金のまま金庫にしまい込むに等しい行動をとった。実際のところは銀行預金や満期まで短い期間しかない国債を買った。つまり高いコストの資金をほぼゼロ金利の資産購入に充当したのである。言い換えれば、経営者はバブルの頃までと同様、内部留保をタダの資金としか考えなかったのである。
そんな企業に投資家は何も期待しない。株価の低迷が生じたのは当然だろう。
2024/10/28